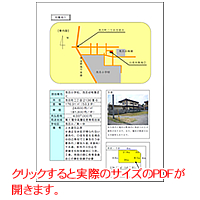『議会基本条例』、『全国都市問題会議』についての報告
| ・『議会基本条例』、『全国都市問題会議』についての報告 |
| 10月6日(水)愛知県岡崎市における『議会基本条例』について、議会事務局の方から説明を受けました。 |
| 『議会基本条例』とは、議会の基本的なあり方を定め、それに基づいた活動を行っていくことにより、市政 |
| の進展と市民の福祉向上を目指していこうという目的で制定されるようです(各自治体で目的は多少異なる |
| と思いますが)。何故、このような条例を定めていこうとする自治体があるかというと、私見ではあります |
| が 議員活動が市民に公開されるケースが少なく、また市民参加の機会が少ないといった理由で議会に対す |
| る不信・不満が市民から有り、それに応えるべく基本条例を策定しているのが要因だと考えられます。岡崎 |
| 市の場合は、まず策定して運用過程で条例をどんどん改定していこうとする考えのもと作られているようで |
| す(初めから高すぎるレベルの条例をつくるよりも)。 |
| この研修を通して感じたことは、議会基本条例を作る・作らないという観点もありますが、まず自らが、議 |
| 員活動を積極的に公開すること(ホームページでの活動報告や市政報告会の開催・活動内容に関するパンフ |
| レットの配布など)を心がけなければいけないと痛感しました。また、市民の皆様の声を吸い上げ市政に反 |
| 映させるように、日頃から市民の方と接する機会を持つことが改めて大切だと思いました。 |

【神戸市での全国都市問題会議にて】
| 7日(木)・8日(金)は神戸市で開催された、全国都市問題会 |
| 議に参加してきました。今回のテーマは、『都市の危機管理~協 |
| 働・参画と総合対策~』でした。ここでは基調講演について報告 |
| したいと思います。 |
| 講師は、明治大学危機管理研究センター所長の中邨章(なかむら |
| ・あきら)さん。演題は『自治体の危機管理~公助と自助のはざ |
| まで~』でした。講演内容とすると、ワールド・バリュー・サー |
| ベイという国際的な比較調査機関の調べでは、日本は先進諸国と |
| 比べて、住民が行政や政治に不信感を持つ割合が多い(もちろん行政や政治が悪いこともあるかもしれない |
| が)。一方で危機が起こった場合に行政・政治を一番頼りにするとの回答が多かったのが日本であった。 |
| しかし、講師いわく『事故や災害の規模が大きくなればなるほど公助(行政・政治)は頼りにならない。 |
| 危機管理では自助が原則である。どのように住民に危機管理を植え付けて行くかが、大きな課題である。 |
| 自助7:共助2:公助1の割合で危機管理意識を持つことが大切である(余談であるが、市政だよりを定期 |
| 的に発行しているのは、日本だけとのこと。したがって市政だよりなどで危機管理意識を向上していくよう |
| に工夫することが出来る)。危機管理は設備でなく、究極的にはヒトの問題である。それは結局ヒトの危機 |
| に対する「認識」・「意識」・「知識」の持ち方であり、これらに「組織」を加えた四識をどう向上させる |
| かが大切である。自治体では平時から職員に緊急時の持ち場と機能を繰り返し周知徹底していくこと。 |
| そして、認識・意識・知識を向上させる研修制度の充実や危機管理に精通する専門職員を育成することが期 |
| 待される。また、顔の見える関係を築いておくことも重要で、大田区では≪20日会はつかかい≫という会議 |
| (関係部署との顔合わせ)が、毎月のように行われている』とのことでした。また、基調講演以外では、震 |
| 災経験のある矢田神戸市長の主報告。一般報告として、京都大学防災研究所巨大災害研究センター長・教授 |
| の林 春男さんの『都市の危機管理』。鹿児島市長の『桜島の防災対策』財団法人建設技術者センター常務理 |
| 事 上村章文さんの『都市の構造変化に対応した危機対応力の向上』を聞きました。会議の2日目はパネル |
| ディスカッションが6名の方で行われました。今回学んだことを伊勢崎市政に反映できるよう一般質問など |
| を通して、行っていきたいと思います。 |