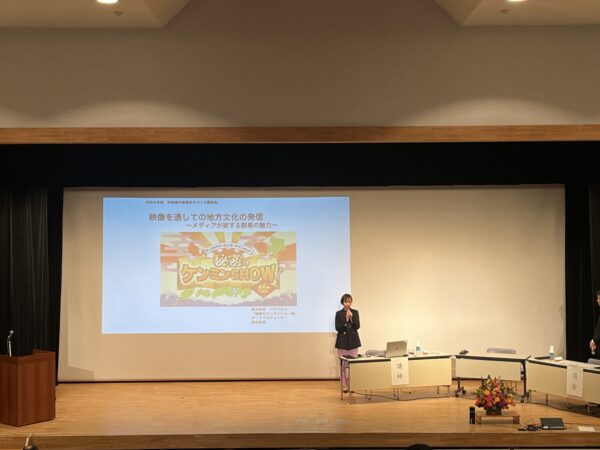令和6年度次世代産業・人材確保に関する特別委員会議事録
6月12日
◆大和勲 委員
群馬県が発展していくためには、労働人口を確保する必要がある。そのために必要なこととして、1点目は働き場を確保しなければならない。働き場を求める20代女性の東京への流出が著しい。2点目として、県外から群馬県に就職してもらうことが必要である。3点目は、子育てをしやすく、教育を充実させることで、移住を促すことができる。子育てと教育のあり方を考えながら、各委員、また委員長のお力添えをいただいて1年間進めていきたい。
社会的情動スキルの調査結果が出たということで、端的にその結果について報告をお願いしたい。
◎角田 学びのイノベーション戦略室長
4月に国際報告書の第1弾が公表され、群馬県の生徒の社会情動的スキルは、性別による差が少なく、家庭の環境による差も少ないと示された。今後公表される報告書を含め、結果を詳細に分析し、令和8年度末までのSEL群馬モデルの確立を目指す。
◆大和勲 委員
社会的情動スキル、非認知能力は、幼児期から育てることが重要である。以前質疑した際、知事は今後群馬モデルをつくると言っていた。群馬モデルをつくるのであれば、そちらにも力を入れていただきたいが、未就学児に対する非認知能力の育成の取組について伺いたい。
◎酒井 義務教育課長
幼児期の非認知能力の育成は重要である。幼児教育で遊びを通して非認知能力を育むことが小・中・高の学びの基盤となる。学校教育の方向性を示したリーフレットに主体性を育む幼児教育等の取組例のページを新設し、トップページに掲載した。資料や研修会を通して幼児教育施設において、取組を進めていただく。
◆大和勲 委員
リーフレットのトップページに載せていただいたということである。幼児教育も含めて幼保小連携していただきたい。特別委員会は縦割りではなく横展開もあるのがいいところである。保育所やこども園での非認知能力の育成についてどのような取組をしているか伺いたい
◎布見 こども・子育て支援課長
私立保育所、認定こども園においても非認知能力の育成は重要である。約8割の保育施設が私立であることから、公立園と格差が生じてはならないと考えている。教育委員会と協力し、保育施設長及び保育士を対象とした研修等を通じて推進していきたい。保育の現場において、個々の子どもに応じた非認知能力を伸ばす取組について、県として提案し、支援していきたい。
◆大和勲 委員
幼児教育で圧倒的なシェアを占めているのは私立の保育所やこども園である。非認知能力を高める取組は、縦割ではなく教育委員会と取り組むことが重要である。私は運営に携わっているからよく分かるが、若い方が勉強をしても、園のトップが変わらない限り方向性は変わらない。施設長に、群馬県が目指している幼児教育の姿を研修等で伝えていただきたい。非認知教育専門家委員会に幼児教育を専門とする委員がいると聞いたが、幼稚園だけでなく、保育園やこども園に携わっている方はメンバーに入っているのか。
◎角田 学びのイノベーション戦略室長
保育の専門家は委員にいないが、群馬大学の幼児教育を専門とする方に委員に就任していただいている。昨年度の専門家委員会において、幼稚園や保育所の具体的な取組を紹介していただき、未就学段階における非認知教育の重要性についても、委員の中で共有しながら議論を進めている。
◆大和勲 委員
現状では、幼児教育の専門家の方から、保育所やこども園の視点でも話をしていただいているようであるが、保育所やこども園についても配慮するようなメンバー構成をお願いしたい。
続いて、保育士配置基準の見直しについて伺いたい。今年から保育士の配置基準が見直されたが、3割の自治体がその配置基準を満たせないのではないかという記事を新聞報道で見た。条例改正に伴う県内の状況はどうか。
◎布見 こども・子育て支援課長
県議会に保育士の配置基準の関係条例について議案を提出しているところである。保育士一人当たりが保育できる児童の数を、3歳児は、20人から15人、4・5歳児は30人から25人に改善するというもので、4・5歳児の配置基準は76年ぶりの改正である。今年4月時点の職員配置の状況についての調査では、県内すべての園で、条例改正後の新基準を満たしていることがわかった。
◆大和勲 委員
県内全市町村で新基準に対応ができていることは、県及び市町村の取組の成果であり、感謝申し上げたい。
保育の現場では、育休明けに年度途中で子どもが入ってくるため、年度末になればなるほど、保育士数が足らなくなる。4月だけでなく、年度途中も調査するなど、今後の調査方法も検討してもらいたい。特に今年は条例改正後はじめての年であるので、そのことについてどのように考えているか。
◎布見 こども・子育て支援課長
今後、国による調査が実施される予定である。また、県では、年に一度指導監査を行うほか、給付金の交付事務等で年に数回確認する機会がある
◆大和勲 委員
手厚い配置ができることが非認知能力の育成についても必要であると思うので、今後も取組を進めてほしい。
10月7日
◆大和勲 委員
2018年の高校入試から外国人という文言を試験要項に明記をしていただいた。そして、今年の入試から外国人が高校に入りやすい環境をつくっていただいた。「外国人生徒等入学者選抜」導入の趣旨について伺いたい。
◎髙橋 高校教育課長
外国人生徒等の入学者選抜は、令和5年度入学者まで海外帰国者等入学者選抜という枠組みで、帰国子女の生徒と同様の選抜で対応してきた。令和6年度の入学者選抜においては、外国人生徒等の入学者選抜についても、本県の高校で学ぶ意欲を持つ、外国人生徒等のニーズに応えるという趣旨の下、従来の海外帰国者等入学者選抜から切り離す形で、外国人生徒等を対象とする新たな選抜制度を設けることとなった。応募資格要件として入国後の在留期間を「6年」とし、日本語の習得期間を十分に確保できるよう配慮するなど要件の緩和を行っている。学力検査についても「国語」を除き「数学」「英語」「作文」「面接」としている
◆大和勲 委員
これから外国人が増える中で、意欲のある方が学べる門戸を広げていることは有り難い。「外国人生徒等入学者選抜」の志願者数はどのくらいか。
◎髙橋 高校教育課長
外国人生徒等入学者選抜の志願者は52名であった。
◆大和勲 委員
どのくらいの方が希望しているかというニーズ調査をしっかりと実施していただきたい。2023年の4月から、高校教育で日本語教育が正式な単位として認められ、外国にルーツを持つ方が多い太田フレックス高校がモデル校になっているが、このモデル校の状況と今後の展開について伺いたい。
◎髙橋 高校教育課長
県立高等学校等における日本語指導の体制づくり事業として、支援を必要とする生徒が多く在籍する太田フレックス高校をモデル校に指定し、外国人生徒等に対する日本語の指導や支援のあり方に関する研究に取り組んでいる。学校内に日本語指導委員会を設置し、専門家の指導を受けながら、対象生徒の指導支援を充実させる体制を整えている。令和6年度からは日本語1Aを開講し、関係する複数の職員が授業づくりや生徒支援について、日本語指導支援員と連携してきめ細かな支援を進めている。
◆大和勲 委員
外国人の方はこれからも群馬県で増えると予想される。教育をベースにあらゆる環境の整備を進めていただき、今後とも外国人が活躍できる環境づくりをお願いしたい。
次に、少子化対策として、結婚につながる出会いの支援が非常に重要である。日本が持続可能な国でいるためには、最低の人口を保っていかなければならない。そのような中で、県としても赤い糸プロジェクト等で結婚や子どもを持つことの良さを発信していることは大変有り難い。新しい取組として、婚活体験レポーターを募集していると聞いた。事業内容とどのくらいの申込みがあったか伺いたい。
◎野村 政策推進室長
当該事業は、結婚を希望する方が、婚活アプリや結婚相談所、婚活イベント等の婚活支援サービスを利用する際に安心して利用できるよう、実際に利用される方などにインタビューし、生の声を体験レポートの形としてまとめ、情報発信するものである。10月6日まで募集し、募集した成婚者2組4名、独身者5名を上回る、成婚者3組6名、独身者9名の応募があった。今後は、アプリの登録項目や婚活イベント当日の様子など、結婚を希望する方を後押しできるような具体的な内容を聴取し、偏りのない情報を発信してまいりたい
◆大和勲 委員
県が絡んでいると安心感がある。マッチングアプリや結婚相談所の体験談を知ってもらうことは重要である。新しい試みであるので、私も今後注視していきたい。安心感というところでは、東京都で結婚支援アプリを始めた。群馬県での実施の考えはどうか
◎野村 政策推進室長
県が実施した少子化対策に関する県民意識調査では、既婚者が結婚相手と知り合ったきっかけは、マッチングアプリとする方が19.8%で一定数おり、出会いの機会として近年注目を集めている。一方、自治体が婚活アプリを運営する場合、多額の開発経費やランニングコストが生じるほか、同種のサービスを多くの民間事業者が提供しており、民間との役割分担の在り方やニーズ、費用対効果等を勘案しなければならない。県としては、結婚を希望する方の望みが叶うよう、民間企業と連携して出会いの機会を提供する「ぐんま赤い糸プロジェクト」や、結婚を社会全体で応援する機運醸成のための「ぐんま結婚応援パスポート」、新たに取り組む「婚活体験レポーター事業」等、総合的に少子化対策を推進してまいりたい。
◆大和勲 委員
民間のアプリの存在や費用対効果の面から実施は難しいと思っているが、アプリを望む県民の意見があるということは承知していただきたい。
12月10日
◆大和勲 委員
こどもまんなか推進プログラムについて伺いたい。県庁の若手職員で構成するチームで、子育て圧倒的ナンバーワンを目指して、プログラムを策定しているとのことだが、現在の進捗状況はどうか。
◎野村 政策推進室長
今年6月にプログラム骨子が決定され、知事から各部局長に対し、骨子を基にこどもまんなか施策の充実に取り組むよう指示が出された。現在、予算編成過程の中で議論されている。プログラムは、群馬の未来を担う若者の育成、全てのこどもの幸福度の向上、子育て世帯の負担軽減、そして社会全体の意識構造改革の4つのテーマに基づき構成されている。プログラムは分野が多岐にわたり、部局を横断する課題に取り組む必要があることから、事務レベルの調整を政策推進室が担っている。各部局では、こどもまんなかの視点を所管事業に取り入れるなど、こども施策の充実に向けた検討を進めている。
◆大和勲 委員
子育て施策には経済的な負担軽減が必要である。子育て支援のメニューは多く、自分がどの対象になっているのか調べないと分からないという声を聞く。児童手当や医療費の無償化等、10年前と比べて格段に支援は充実している。国、県、市町村が取り組んでいる支援策の効果が分かりやすく見えるとよいと思うがどうか。
◎野村 政策推進室長
こどもまんなか推進プログラムの各事業は、こども計画の事業実行計画として位置付けられ、一体的に取り組むことになる。事業効果については、計画の評価において県が実施する「少子化対策に関する県民意識調査」で検証が可能である。
◆大和勲 委員
若手の当事者が考えているということで、しっかりとしたプログラムができることを期待している。
令和7年3月5日
◆大和勲 委員
まず、こどもまんなか推進プログラムの作成に携わっていただいた方に感謝申し上げたい。来年度予算における保育充実促進費補助金について、補助制度の概要を伺いたい。
◎布見 こども・子育て支援課長
1歳児4人に対して1人の保育士を配置し、補助要件を満たした保育所等に人件費の一部を補助する。補助単価は、施設規模に応じたスライド方式とし、制度の開始は令和7年10月からである。なお、現行の5対1の補助制度は維持する。
◆大和勲 委員
開始時期を令和7年10月とした理由を伺いたい。
◎布見 こども・子育て支援課長
非認知能力の育成に取り組むこと、及びインクルーシブ保育に取り組むことの2つが、4対1補助の新たな条件である。保育士の確保に時間がかかるため、準備期間が必要ではないかと考えている。また、市町村としても、制度改正の周知と財源を確保する期間として見込んだところである。
◆大和勲 委員
こども園や保育所は人材的に余裕がないため、準備期間を設けていただいたことは有り難い。非認知能力の育成に取り組むという要件についても、この委員会で議論したことを早速取り入れていただいたということで感謝したい。非認知能力の育成に係る要件について、具体的な考えを伺いたい。
◎布見 こども・子育て支援課長
補助要件とした「非認知能力の育成」及び「インクルーシブ保育」への取組は、1歳児のみならず、全ての園児に質の高い保育を提供することを目的とし、園全体での意欲的な取組を推進するものである。非認知能力の育成については、園の保育目標に掲げていること、及びその目標に具体的に取り組んでいることを要件とすることで想定している。インクルーシブ保育については、障害者手帳を持つ子どもを受け入れていることや、研修会の実施等、様々な事例から2つ程度取り組んでもらうことを想定している。
◆大和勲 委員
非認知能力の育成について、市町村教育委員会の管理職ではない職員や、こども園・保育所の副主任、担当の先生も研修等の対象に入れていただければ、非認知能力育成に係る県内認知度が上がってくると思うので提案させていただく。
続いて、こどもまんなか推進プログラム搭載事業一覧にある「子育て世帯に優しい県営住宅の管理・活用」について、今後の意気込みを伺いたい。
◎五十嵐 住宅政策課次長
国土交通省が定めた公営住宅を活用した、住まいの子育て支援実施要領では、子育て・若者夫婦世帯に対する優先入居の促進や、収入基準の緩和を図ることなどを、各自治体が積極的に検討し、措置を講じることとされている。本県県営住宅においては、これまでに、入居要件である収入基準の収入金額の基準を緩和し、人気の高い団地における子育て世帯の当せん倍率を2倍にする優遇措置を導入する等、子育て世帯の入居に関する対策を講じている。これらの支援に加え、子育て世帯のみが入居できる、子育て支援住宅を130戸設定してきた。今後は国が策定した要領や、先進事例を参考にしながら、新たに若者夫婦世帯を対象に加え、子どもを産み育てやすい住まいを確保できるよう、プログラムに沿って推進していきたい
◆大和勲 委員
具体的な施策が進むようお願いしたい。子育てを子育て世帯に押しつけるのではなく、社会全体で負担を分け合って子育て支援を行わなければ、少子化の傾向には歯止めがかからない。我々も県民の皆さんに事業の周知を行っていきたい。
また、本日雪が降った関係で、昨日保護者に小学校の登校が1時間遅れるとのメールがきた。児童の安心安全のために致し方ないことではあるが、こどもを一人だけ家に残すわけにはいかない方もいると思う。児童クラブで預かれない場合もあるため、学校で預かってもらうことも検討していただきたい。こちらについては、要望とさせていただく。
次に、高齢者の働き方について伺いたい。今後生産労働人口が減っていく中で、高齢者がどのように働いていくかということが重要である。群馬県シニア就業支援センターの利用状況はどうか。
◎田村 労働政策課長
群馬県シニア就業支援センターにおいては、アドバイザーを置き、就労を希望する中高年齢者からの相談対応やマッチングを行っている。実績としては、直近5年間程度で年間約500人から相談をいただき、そのうち約70人が就業している。
◆大和勲 委員
組織や会社によっては1日の勤務時間を減らすなど環境整備が必要であると思う。他県ではそういった取組を実施している企業を評価する制度を実施している例もある。高齢者の働きやすい環境を整えるために、県として今後どのように取り組んでいくのか伺いたい。
◎田村 労働政策課長
働く意欲のある高齢者は多いが、5日間連続で働くのは大変であるという声も聞く。県内企業に対し、柔軟な勤務体系の整備により高齢者が活躍している好事例を紹介していく。また、県では群馬県いきいきGカンパニー制度を設けており、ワーク・ライフ・バランスの推進に積極的な企業を認証している。引き続き、多様な人材が働きやすい環境整備を促していきたい
◆大和勲 委員
健康寿命が延びるとともに、体力面でも良好な状態が継続しているというデータもある。生産労働人口が減少していく中で、高齢者が働く体制づくりに取り組んでほしい。