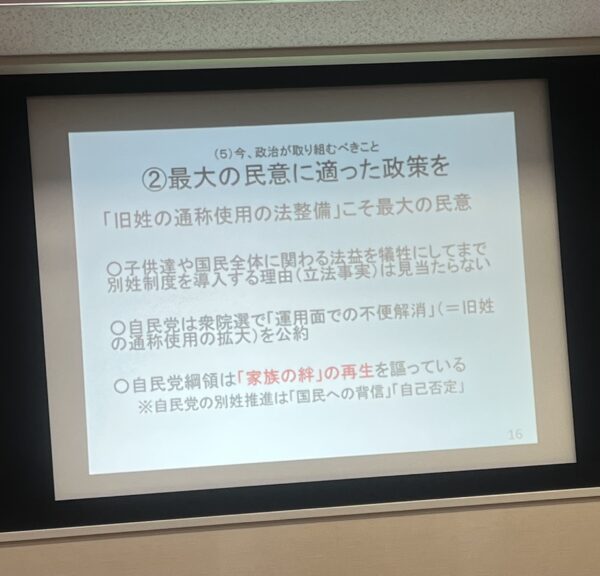令和6年度常任委員会質疑答弁(総務部関係)
令和6年6月5日
◆大和勲 委員
補正予算について、補正後の県税収入2,700億円は過去最高と伺った。総務部長をはじめ、徴収に関わる職員に御礼申し上げたい。新たな事業には自主財源の確保が必要であり、ぜひ令和6年度もしっかりと取り組んでもらいたい。
外形標準課税の見直しについて、県内で対象となる法人数の推移はどうか。
◎塩野 税務課長
群馬県に申告のある外形標準課税の対象となる法人数は、令和5年度は1,655法人である。制度導入当初の平成16年度は2,178法人であり、比較すると4分の3程度まで減少しているが、群馬県では極端な減資を行った例は認められておらず、景気の動向や経済構造の変化によるものと考えられる。
◆大和勲 委員
外形標準課税対象法人の適正な課税に向けて、どのように取り組んでいるか。
◎塩野 税務課長
法人の県民税・事業税は、一般的な法人については国税に準拠しているが、外形標準課税等の対象となる一部の法人については、県が独自に調査を行い、課税標準額の決定、更正を行う。調査には課税や会計事務の知識が必要となるため、調査専任の法人調査係を配置し、法人へ直接訪問して帳簿の確認などを行っている
◆大和勲 委員
しっかりと調査を行い、適正かつ公平な課税と財源の確保に向けて取り組んでいただきたい。
10月3日
◆大和勲 委員
ますは、消防団の皆様の活動に感謝申し上げる。全国的にも消防団員が減っているという新聞記事があった。本県の消防団員の推移について、併せて機能別消防団員についても伺いたい。
◎植野 消防保安課長
令和4年に11,001人であったが、今年度の4月1日時点では10,630人と、371人減少している。機能別消防団員については、令和4年が363人、令和6年は494人と、131人の増加となっている。
◆大和勲 委員
消防団員の充足率については常々取り上げられており、地域の安心安全を守るため災害時も含めて大変尽力いただいているところだが、農業従事者や自営業者の減少、地域との関わりが薄くなったことなどが、団員の減少につながっている。
消防団員が利用することでメリットを受けられる、消防団応援の店について伺いたい。登録店舗数の推移はどうか
◎植野 消防保安課長
消防団員への優遇サービスを提供する企業・店舗を募り、消防団応援の店として登録している。近年の推移としては、令和4年に277店、令和6年に284店と増加している
◆大和勲 委員
7店舗の増加ということで、頭打ちとも、まだまだ増やせるとも考えられるが、消防団員の充足という面からも、市町村を含めてぜひ働きかけをお願いしたい。
また、消防団OBについて、正規の団員が少ない中で地域に根付いたOBが実際に活躍しているが、現場での活動時の怪我への補償がどのようになっているか伺いたい
◎植野 消防保安課長
消防活動での怪我について、常備消防や消防団が到着する前に消火活動を行った場合など、活動に従事いただいた方は要件を満たした場合に消防作業従事者として定義され、公務災害の対象となる。また、常備消防や消防団の到着後も、その指示に従って作業に従事した場合には補償の対象となる。
◆大和勲 委員
補償の対象になる活動について、現場の消防団にあまり知られていないのではないかと思う。本来は正規の従事者で対応すべきかもしれないが、実際にこういったOBの方に活動いただくことは非常に重要だと思うので、ぜひ周知いただきたい。
続いて、災害時の避難所運営について伺いたい。日頃から災害時のトイレやキッチンについて大変熱心に取り組まれている議員に心より敬意を表する。自民党も令和2年に県の避難所運営検討会の委員になり、有識者を招いて講演会を行った。自分は当時、危機管理特別委員会の委員でもあり「暖かい食事を提供できる避難所を」という提言をした。6月に新聞でキッチンカー団体との協定という記事を見たが、取組状況や今後の考え方などを伺いたい。
◎飯塚 危機管理課長
県の避難ビジョンの中でも、温かい食事というのは、分散避難の推進と合わせて避難生活の向上という柱の1つとして目標にしている。委員お話のとおり、6月にキッチンカー事業者団体と協定を締結し、災害時に派遣を要請すれば避難所の被災者に温かい食事を提供できることとなった。協定を結んだだけでなく、実際にスムーズな運用ができるよう、今後、防災訓練等の機会を通じて実効性を高めていきたい。
◆大和勲 委員
温かい食事は、被災者の体調面だけでなく精神面でも助けになる。このような取組に感謝申し上げるとともに、この仕組みに協力している、まきばプロジェクトは、地域活性化の面でも非常に尽力している団体であるため、こういった方からもぜひ避難所運営について意見を吸い上げてもらえればと思う。
先ほど防災訓練での運用という話があったが、今年度の前橋市での総合防災訓練ではどうか。
◎飯塚 危機管理課長
今回は想定していない。今後機会を捉えて、また、機会がなければキッチンカーだけでも実働の訓練を計画したい。
12月6日
◆大和勲 委員
昨日の委員会でも行財政改革大綱の素案が示されていたが、歳入の確保は非常に大切である。未利用地の現在の状況や、過去の売却実績についてはどうか
◎寺田 財産有効活用課長
現在の未利用地は、43か所で約31.6haである。未利用地が発生した時は、まず公共的な利用を検討し、次に民間への売却により歳入確保や管理コストの削減を図っている。売却実績は、過去10年間で68物件、約19.4haで、約40億円の収入となっている。
◆大和勲 委員
不要のものや、今後使わないものをしっかりと売却していくことが大変重要である。今まで売れなかった未利用地については、少し発想を変える必要があると思う。ぜひ工夫をしていただきたい。
旧伊勢崎合同庁舎跡地の現状についてはどうか。
◎寺田 財産有効活用課長
旧伊勢崎合同庁舎は平成30年に機能を総合教育センター内へ移転し、跡地については令和元年度に入札でハウスメーカーに売却したが、造成工事中に埋設物が発見されたため、契約解除により、一部の土地が返還された。
この周辺は住宅も多く、宅地として活用されることが地域にとっても良いと考えている。改めて売却に向けて埋設物の調査を行っており、その結果を見て、手続きを進めたい
◆大和勲 委員
今の答弁によれば、地下の埋設物についての調査結果はまだ出ていないということである。地元の方々は区長をはじめとして、どうなるのか心配している。決まってからではなく、現在の進捗状況を含めて、丁寧な説明をお願いしたい。
もう1点質問したい。長野県で「決断~火の見櫓に登った男たち~」という映画が製作され、2019年の台風19号における災害対応時の消防団員の葛藤が描かれており、様々なメッセージが込められている。消防団の活動においては、安全管理は非常に重要なテーマだが、消防団員への安全教育の状況はどうか。
◎植野 消防保安課長
消防団員の安全教育については、主に消防学校で実施している。消防学校では、団員の経験年数や職務に応じた安全管理等の教育を行っている。災害現場では危険要素をゼロにすることはできないが、自分も仲間も負傷者を出さないで消防活動を行わなければならない。消防学校では、常に安全に対する配慮と確認をしながら消防任務に当たれるよう安全管理の重要性について教育しており、引き続き、適切に取り組んでいきたい
◆大和勲 委員
映画の内容に対する感想はどうか。
◎植野 消防保安課長
台風の増水により堤防が決壊する直前の避難誘導を行った消防団員の対応について、様々な視点やメッセージが込められたものであり、活動する上で重要な安全管理に対する視点も含まれていたと思う。
◆大和勲 委員
消防団員の安全教育について、今まで以上にしっかりと取り組んでほしい。
令和7年3月12日
◆大和勲 委員
林野火災に係る予防対策の取組状況を伺いたい。
◎福田 消防保安課次長
岩手県大船渡市の林野火災などを踏まえ、県から各消防本部に対して、林野火災警戒強化に関する通知を行っている。各消防本部では、消防団とも連携しながら火災予防活動を実施し、消火体制も整えている。特に林野周辺の住民や入山者等に対し、火災に対する意識の高揚を図っている。また、3月6日の知事定例記者会見において、林野火災等の火災予防の注意喚起を行ったところである。引き続き、各消防本部や市町村等と連携しながら、火災予防活動に努めてまいりたい。
◆大和勲 委員
被災地での経験は有用であることが多いので、大船渡市で消火活動に当たった人から火災対応の状況を確認し、今後に役立ててほしい。
知事戦略部
6月7日
◆大和勲 委員
高校生リバースメンターについて伺いたい。
昨年度もいろいろな議論があったようだが、若者の政治参加という視点で、大変良い取組だと思う。今後もぜひ成功事例をしっかりと発信してもらいたい。また、成功事例については市町村へも情報提供すべきと思うが、どうか。
◎山中 総合計画・EBPM推進室長
成功事例の周知について、市町村への情報提供は行っていなかった。今後改めて検討したい
◆大和勲 委員
若者の政治参加について、我々議会もしっかりやらねばならないが、行政も力を貸していただければと思う。
続いて、県有施設の脱炭素について伺いたい。ESCO事業について、財政的なメリットから市議会議員時代から取り組んでいるところであり、伊勢崎市の防犯灯にも取り入れていただいた。県でも、女子大や近代美術館でESCO事業を取り入れたと聞いている。当初予算の補正で、県有施設のLED化として6億2,600万円を計上しているが、こちらはLEDのリース方式とのことで、なぜリース方式を採用したのかを伺いたい。
◎小林 グリーンイノベーション推進課長
ESCOとリースの最大の違いとして、省エネの保証とマネジメントの有無がある。事業者のスキルによって省エネの量が変わってくるため、プロポーザルをかけることになるが、今回のLEDでは、マネジメントという点であまり効果が現れない。それを踏まえて経費やスピード感の面から、リース方式が適切と判断した。
◆大和勲 委員
リース方式を選択したことによる経費や電気代の削減について、しっかりと効果測定をしていただきたい。また、LEDについては2030年までという目標もあるため、スピードアップが必要である。
今回、県立学校や警察、合同庁舎でのLED化を図るとのことだが、第2弾としてどのような施設を考えているのか。
◎小林 グリーンイノベーション推進課長
県庁舎は既に100%近くLED化している。県有施設全体では2030年までにという目標を掲げている。第1弾では、リース事業として導入しやすいところを選定した。施設によりそれぞれ特性があるため、各施設から話を聞きながら、今後も、まずは入れやすいところからという形になる。
◆大和勲 委員
市町村にも広めることが重要と考える。今回の照明LED化について、こんなやり方があるという形で市町村へ横展開をすべきと思うが、どうか
◎小林 グリーンイノベーション推進課長
御指摘のとおり、脱炭素を進めていくに当たっては、市町村や民間との連携が非常に重要と捉えている。昨年度から市町村と県の連携を図るため、県と全市町村で群馬地域脱炭素連携チームを組み、講演やワークショップを行っている。今年度の取組の一つとして、部活のような活発な議論ができる形でLED部を設けた。全ての市町村が入っているわけではないが、ここで先行自治体の事例を作り、他の市町村にも広げたい。
◆大和勲 委員
全県で脱炭素を進めるにあたっては、県だけではなく市町村も連携しながら進めていく必要があるため、横の連携強化を図るようお願いしたい。
続いて、今年度の地域外交の予定についてお伺いしたい。
◎奈良 地域外交課長
知事が目指すトップ外交は、自らが海外に赴いて外国政府のトップと話をする、新しい地域外交であり、今年度もその方針は変わらない。訪問先は現在検討中であるが、関係構築を進めている米国、ベトナムなどが候補になっているほか、欧米の現地企業を訪問することも考えている。
◆大和勲 委員
知事が訪問した町との交流について、深く交流していくか、いろいろな地域と広く交流していくかなど、どのように考えているか。姉妹都市のような考えはあるか。
◎奈良 地域外交課長
今まで実施したトップ外交で、各国地方都市との交流を進めてきたところである。米国インディアナ州とは、令和4年9月に交流に関する覚書を締結し、経済・教育・文化、人材育成の面で交流を深めるため、様々な事業を展開している。ベトナムのハナム省とも昨年12月に覚書を締結し、経済分野を中心に交流を深めており、各地域での交流については、県内市町村にもつないでいきたいと考えている。
また、姉妹都市制度は幅広い分野での交流を進める取組であるところ、現状では、まずは特定の分野での交流を深化させることに注力し、将来的には姉妹都市という可能性も見据え、交流を進めたい。
令和7年3月11日
◆大和勲 委員
湯けむりフォーラムについて、今年度の特徴及び取組の効果、実績について伺いたい。
◎佐藤 未来創生室長
湯けむりフォーラム2024は3つの特徴が挙げられる。
1つ目は、これまでは招待制であったが、一般参加プログラムを導入したことである。Day1のコンサートホールや、Day2の御座之湯企画では、一般公募を行い約90名が参加した。御座之湯企画では、湯路広場でパブリックビューイングも行った。また、フォーラムの様子を紹介する群馬テレビの特別番組を制作した。他県のテレビ局で放送を行うとともに、YouTubeでのアーカイブ配信は1万回以上、ショート動画は15万回以上の再生回数があった。これらの取組により、県内外の多くの方に湯けむりフォーラムや群馬の魅力を知ってもらうことができた。
2つ目は、四万温泉、八ッ場ダムなどを巡るリモートバスツアー「ニコニコバスツアー」を実施し、草津温泉以外の温泉地もPRした。
3つ目は、民間企業と連携した企画を実施したことである。東映と強力なタッグを組み、トークセッションや分科会を実施するとともに、県と東映のIPを活用したノベルティを製作し、参加者に配布した。また、地元の上毛新聞やエフエム群馬とも連携した。
◆大和勲 委員
私も参加をさせていただいたが、寺島実郎氏の話は大変勉強になった。食と農、医療と防災に着目するという話の中で、高付加価値コンテナの製造や設置について言及があった。部局は異なるが、危機管理課で「命のコンテナプロジェクト」も始まっているということで、理解が深まった。
群馬県は首都圏に近いので、移住・定住に取り組むべきであり、子育て先進県を目指した方がよいのではないかとの話もあった。そういった中で、これも部局が異なるが、県では「こどもまんなか推進プログラム」について取り組んでいただいており、方向性の合った施策が実行できていると感じた。
本県産業は自動車関連産業の一本足打法なので、デジタル・クリエイティブ産業が必要なのではないかという話もあったかと思うが、これも先週の知事の定例記者会見において、なぜデジタル・クリエイティブ産業が必要なのかという話が出ていた。新たな富を生むための取組について、寺島氏にお話いただくことで我々の理解も深まったのではないかと思う。
SEL分科会にも参加させてもらったが、特に伊勢崎高等学校が良い取組をしており、勉強になった。
YouTubeでは1万回以上、ショート動画については15万以上の再生回数があったようだが、大変多くの方に視聴いただいているということなので、予算を投じて湯けむりフォーラムを開催し、県の取組を県民に知っていただくことは大変意義深いことである。
自民党から要望した草津温泉以外との連携も対応してもらい感謝している。他の温泉地とタイアップすることは、温泉文化のユネスコ無形文化遺産登録の一助になるので、令和7年度もしっかり取り組んでほしい。
次に、こどもまんなか推進プログラムにも記載のある「子育て応援番組」について伺いたい。最近、子育ての大変な部分についての報道が目立つと感じているが、「子育て応援番組」なのだから、子育ての楽しさなども踏まえて制作してほしい。同番組について、現時点で決まっていることについて伺いたい。
◎瀬下 tsulunos室長
「子どもが安心して過ごせる居場所づくり」につなげるため、子育て世帯が楽しめる教育エンターテイメント番組の制作・放送を想定している。具体的には、令和7年度の下期に、15分番組を週1回程度の頻度で放送する予定である。子どもの情緒や表現、言葉や身体の成長を応援するとともに、子どもが楽しめる施設や群馬県の魅力なども紹介したい。また、より多くの方に見てもらえるようネットメディアも活用していく予定である
◆大和勲 委員
これから番組制作に向けて、いろいろな協議が行われると思うが、子育ての楽しさ、やりがい、充実感を伝えることが少子化対策にもつながると思うので、そのような番組をつくってもらえると有り難い。
また、視聴率上昇や認知度向上にもつながると思うので、県民参加型の番組づくりをお願いしたい。
地域創生部
12月5日
◆大和勲 委員
先ほど説明のあった県民会館について伺いたい。まずは、第3回前期定例会において一部趣旨採択された請願を踏まえ、県民に広く意見を聞くためのアンケート調査を実施いただいたことに対して、御礼を申し上げる。
アンケート調査の内容について、認知度等はどのように測るのか。より具体的に教えていただきたい
◎佐藤 文化振興課長
アンケートのはじめに、最後に利用したのはいつか、直近10年で何回利用したか、大ホールや小ホールなどの利用場所及び目的は何だったかという利用状況についての設問があり、次に、利用して良かった点、良くなかった点についての設問がある。
その上で、まず、県民会館が必要な施設であるかどうかについて、率直に聞く設問を用意している。さらに、利用者数の推移や改修費用等の経費に関する情報を加味した場合の県民会館の必要性についての設問があり、最後に自由意見としている。
◆大和勲 委員
アンケート調査の中に利用状況や修繕などの情報を付け加えることは、回答に当たり大変参考になると思う。
アンケート調査は1,000名に回答をお願いするのか、それとも1,000名分の回答を求めるのか。
◎佐藤 文化振興課長
1,000名分の回答を収集するもので、回答数が1,000に達すると自動的に終了となる。地域や年齢、性別で、均等に意見を集めることとしている
◆大和勲 委員
アンケート調査の結果は、いつ頃県議会に情報提供があるのか
◎佐藤 文化振興課長
アンケートは現在実施中であり、結果をまとめられる時期については未定である。請願の一部趣旨採択を踏まえたアンケートであり、結果は県議会に報告したい。
◆大和勲 委員
我々もいろいろな調査をしているが、1,000名分の回答があれば精緻な数字が出てくるのではないか。いろいろな年代、地域に聞いてもらうのは良いことだと思う。結果はまた教えてほしい。
県民会館を令和7年度から予約停止することについて、ネーミングライツを取得しているベイシアには説明しているのか。
◎佐藤 文化振興課長
利用停止について、事前に説明している。利用範囲を大ホールのみに縮小した際も、条件面等について相談し、理解を得ている。
◆大和勲 委員
非常にコスト意識がある会社で、群馬県発祥でもある。是非ベイシアの意向も酌み取って進めてもらえると有り難い。情報提供も含めてよろしくお願いしたい。
次に、伝統文化の継承について伺いたい。「群馬のふるさと伝統文化支援事業」補助金の実績と活用状況はどうか。
◎佐藤 文化振興課長
令和4年度は、予算額800万円に対して13件228万9千円、令和5年度は、予算額600万円に対して21件333万円の実績であった。今年度は、予算額600万円に対して35件599万3千円を交付決定している。なお、補助内容は、道具・衣装等の購入・修繕に関するものが多い。
◆大和勲 委員
伝統文化を継承するための課題について、県はどのように考えているのか。
◎佐藤 文化振興課長
令和5年度に県教育文化事業団が伝統芸能団体に対して実施した調査では、回答があった155団体のうち、「後継者育成が順調ではない」と答えたのが67%であった。
少子高齢化や過疎化等により後継者が不足し、伝統文化の継承が困難となっている。伝統文化の担い手を増やしていくためにも、子どもたちが伝統文化に触れる機会が重要と考える。
◆大和勲 委員
今、67%の団体が後継者育成について課題があるとの答弁があった。そういった中で、今年の秋、地元である茂呂小学校運動会に行ってきたが、その中で一番感動したのは、約120名の5年生による千本木竜頭神舞であった。
学校と連携して、伝統文化を守っていくことが重要だと思うが、文化振興課としてはどのように考えているのか。
◎佐藤 文化振興課長
子どもたちが、伝統文化・伝統芸能を通じて、地域の人と交流し、郷土愛を育み、ふるさとに誇りを持つことは重要と考える。学校現場も忙しいと聞いているが、教育委員会とも相談して、取組を検討していきたい
◆大和勲 委員
学校側の多忙化解消等、いろいろやるべきこともあるので強制はできないと思っているが、伝統文化を守っていくことや、地域との交流を図ることは意義あることなので、機会があれば私も教育委員会に働きかけたい。
もう1点伺いたい。外国人との共生のためには、外国人が医療を受けやすい体制をつくっていくことが大前提にあると思うが、JMIP(外国人患者受入医療機関認証制度)の認証を受けた医療機関が県内にはない。このことについて県としてどのように考えているのか。
◎佐藤 ぐんま暮らし・外国人活躍推進課長
委員御指摘のとおり、外国人患者が安心して医療機関を受診できる体制を整えていくこと大切であると考えている。受入体制の整った医療機関が増えていくことが望ましいので、医務課とはこれまでも情報共有しているが、引き続き連携して取り組んでいきたい。
◆大和勲 委員
単にJMIP(外国人患者受入れ医療機関認証制度)の認証を受けた医療機関が県内にあればよいということではなく、やはり外国人県民や外国人観光客の方にとって何が良いのかということだと思うので、外国人の方々が活躍できる体制づくりのため、ぜひ研究していただきたい。
令和7年3月11日
◆大和勲 委員
移住希望地ランキング発表後の、ぐんま暮らし支援センターの相談対応状況はどうか。
◎佐藤 ぐんま暮らし・外国人活躍推進課長
移住希望地ランキング発表前後で、相談件数が約3倍に増加した。現状では対応できているが、引き続き増加が見込まれるため、状況に応じて必要な対応を検討していきたい。
◆大和勲 委員
現状は対応できているとのことだが、対応できず相談件数が上がらなかったということがないように、ぜひお願いしたい。
もう1点、新規事業である「親子でテレワーク移住体験」について、具体的にどのような方法で実施するのか。
◎佐藤 ぐんま暮らし・外国人活躍推進課長
子どもの受入れについては、市町村が保育園等と調整し、一時預かりを行う方法を考えている。実施地域については、全市町村に意向を確認し、実施を希望する桐生市との連携を予定している。次年度以降も、市町村の希望に応じて実施地域を検討していきたい。
◆大和勲 委員
一時預かりの仕組みを使うということだが、市町村にもよく仕組みを説明してもらえると有り難い。桐生市で成功事例をつくって、実施地域を拡大してほしい。